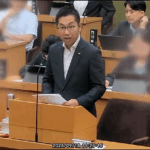市立ひらかた病院の8.9億円赤字危機!北河内医療を守るための緊急提言
少しタイムラグが生まれてしまいましたが、9月定例月議会にて市立ひらかた病院の赤字に対して提言を行っています。まずはサマリーを動画にてまとめているのでご覧ください☟
市民の皆さまにとって安心・安全な医療を提供し続けることは、市立ひらかた病院の責務であり、北河内唯一の公立総合病院として、その役割は非常に重要です。
しかし、現在の病院経営は極めて危機的な状況にあります。本定例月議会では、市立ひらかた病院の経営と人材確保について質問させていただきました。
この危機を脱し、地域の医療を未来にわたって守り抜くための私の提言を、皆さまにお伝えします。
🚨 起きている現状
市立ひらかた病院は、非常に厳しい経営状況にあります。
- 令和6年度決算で、約8億9千万円もの赤字を計上しました。
- この赤字の背景には、全国的な物価高や人件費の高騰に加え、看護師不足による一部病棟の休棟が大きく影響しています。
- 人材確保の取り組みにより、小児病棟である4階西病棟は昨年9月に再開棟しました。また、6階西病棟についても、看護師の採用数が再開に必要な数を上回ることができ、令和8年秋以降の再開棟を目指すこととなりました。
- 経営改善として、手術件数向上や外来診療の見直し(タスクフォース立ち上げ)による収益確保や、医療機器購入費の約5,000万円抑制など、歳出削減にも取り組んでいます。
📉 その背景にある課題
病棟の再開に向けた採用活動は大きな成果ですが、短期的な対策だけでは危機を脱することはできません。
- 看護師の人材確保は全国的に厳しい状況であり、病棟を休棟せざるを得ない状況は、病院経営にとって極めて望ましくない状況です。
- 採用活動が功を奏した一方で、今後は大量採用に伴う受け入れ側や入職者へのストレスに配慮が必要となります。
- 収益の確保、歳出の削減は進んでいますが、現状の赤字を解消するほどの大幅な収益増加が短期間で見込めるかは不透明であり、抜本的な経営改善が喫緊の課題です。
- 現行の経営強化プランにおいても、この北河内医療圏は急性期機能が過剰な状況にあると指摘されている点も重要です。
🌐 社会的な現状について
市立ひらかた病院は公立病院として地域の医療を支える責務がありますが、その「あり方」自体が社会的なテーマとなっています。
- 全国的に、公立病院を含めた医療業界全体の経営が、物価高や人件費の高騰で厳しい状況にあります。
- 世界的に見ると、日本は病床数が多すぎる、人口減少に見合っていないという指摘があり、病床の適正化は国としても大きなテーマです。
- このような社会情勢を踏まえ、大阪府から示される新たな地域医療構想や、来春に予定される次期診療報酬改定を待って、市立ひらかた病院が地域において担うべき役割が今後検討されることになります。
🚀 大浜からの提言
市立ひらかた病院の経営を改善し、北河内医療を守るため、私は以下の3点を強く提言します。
1. 👩⚕️ 職員への「投資」を最優先に!
病院は投資型であり労働集約型産業です。厳しい状況だからこそ、職員の皆さまへの投資を積極的に行うべきです。
- 職場環境の改善:市役所のエンゲージメント調査や教育委員会の「笑顔の学校プロジェクト」など市の取り組みを参考に、看護師向けのアメニティ拡充や休憩スペースの充実など、ソフト・ハード両面で職場環境の充実を継続して行うべきです。
2. 🏥 病院の「あり方」に関する真剣な議論を!
現状の赤字額が拡大し、改革プランとの乖離が増加していくのであれば、今の急性期中心の役割を堅持するだけでなく、複数の選択肢を真剣に検討すべきです。
- スリム化の検討:病床を返還し、病院の規模をスリム化する。スリム化することで、病室の個室化を進め、入院患者の満足度や医療の質を高めることも可能です。
- 機能替えの検討:急性期以外の役割への機能替えを目指す。(具体的には地域包括ケア病棟など)
- 現行の役割の維持:地域の急性期としての役割を維持(強化)する。
3. ⭐ 急性期維持なら「加算」を狙う戦略を!
もし地域の急性期としての役割を維持する路線を選ぶのであればより戦略的に経営を進めるべきです。
- 更なる急性期加算の取得:「総合入院体制加算2」など、更なる急性期加算を狙うべきです。
https://ohama-yosuke.net/621/ - 逆算での投資:コロナ禍で高額な医療機器を購入されていますが、本来は施設基準や診療報酬の加算を見据えて、逆算で必要な投資を行うべきです。
来年以降、診療報酬改定や新たな地域医療構想が示される中で、市立ひらかた病院が今後地域で担うべき役割について、引き続き議論を重ねてまいります。
市民の皆さまの健康と、北河内医療を守り抜くために、今後も全力を尽くします。